
新入荷
再入荷
志ん生のいる風景 矢野誠一 中村吉右衛門 安藤鶴夫 三木助 戸板康二 文楽 菊五郎 山口瞳 小さん 談志 金馬 川上哲治 倉本聰 志ん朝ほか多数
 タイムセール
タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(※)
999円以上お買上げで代引き手数料無料
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
商品詳細情報
| 管理番号 |
新品 :91658151598
中古 :91658151598-1 |
メーカー | ac0f8df9 | 発売日 | 2025-04-09 19:29 | 定価 | 3280円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||













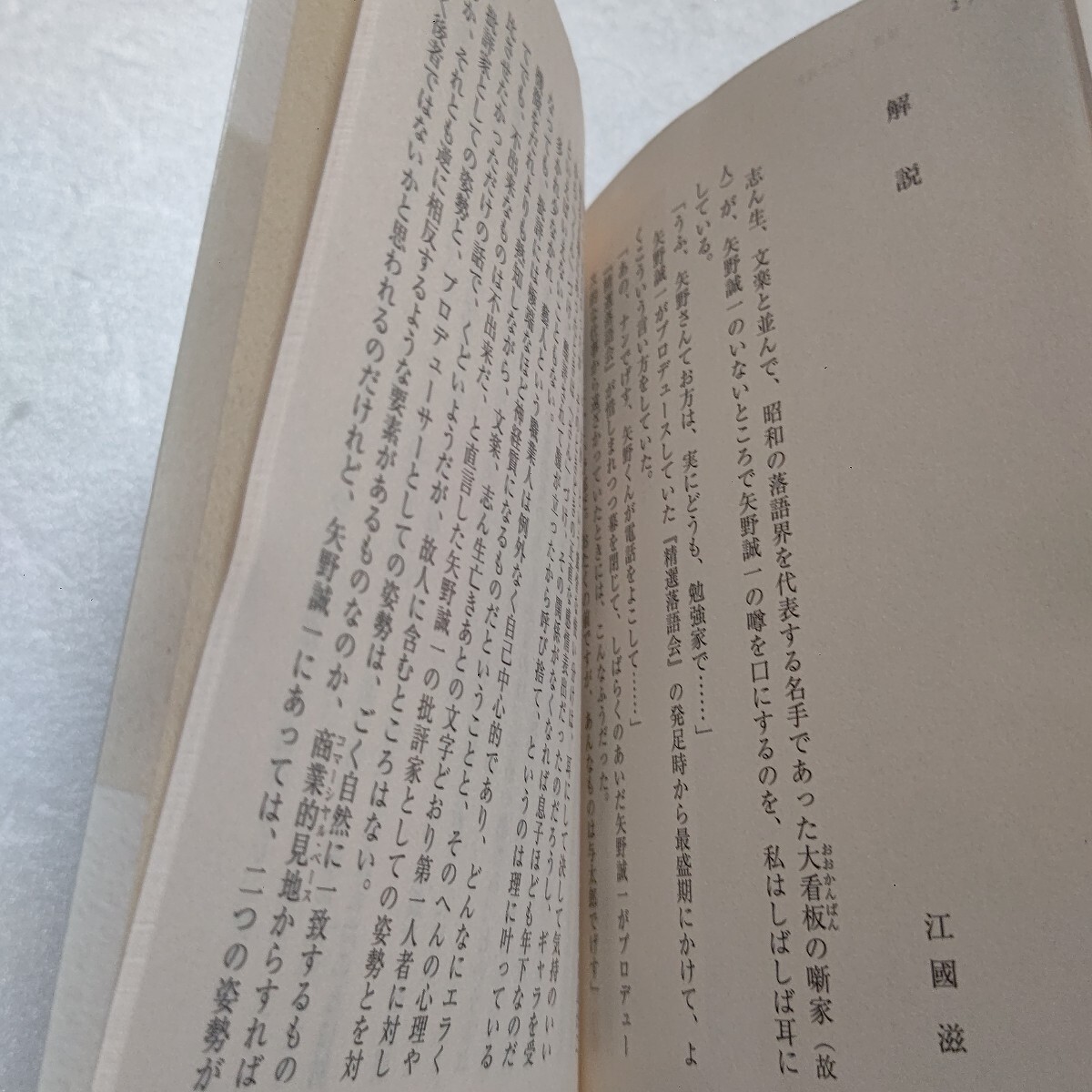
























志ん生のいる風景 矢野誠一
落語会の仕掛け人としても「昭和の大名人」と付き合った著者による名著。強烈な自我がもたらす圧倒的な魅力。
内容説明
臨機応変、独特の間、フラ、現代性などで一世を風靡し、今なお落語の第一人者の名声を不動のものにしている昭和の大名人の、魅力の依ってきたるところを、その生前、「精選落語会」の企画者としても交際の深かった著者が、達意の文章で的確に表現した名著。業と自我を、最高の藝にまで昇華させた落語の神様の軌跡を追う決定版評伝。
登場する方々
中村吉右衛門 安藤鶴夫 桂三木助 戸板康二
桂文楽 久保田万太郎 尾上菊五郎 山口瞳
小泉信三 夏目漱石 金原亭馬生 柳家小さん
三遊亭圓生 林家正蔵 三遊亭夢楽 可楽
三遊亭柳朝 立川談志 三遊亭金馬 樺美智子
林家照蔵 川上哲治 倉本聰 結城昌治
加藤武 古今亭志ん朝 橘家圓太郎 桂三木助 林家三平 リーガル千太 双葉山 美濃部孝蔵 柳家小せん 石井英子 江國滋 林家正蔵
橘家圓喬 桂小南
三遊亭朝太 小円朝 結城昌治 柳家小三治
柳屋三亀松 林家正楽 桂小文治 立川談志
松鶴 桂文枝 小沢昭一ほか多数
レビューより
時が過ぎ、馬生、志ん朝さえもいない今、志ん生のいた風景を知る世代にも知らない世代にも、志ん生の噺に改めて鮮度を与えてくれる1冊。
志ん生師匠についての思い出話.
大雑把に時系列に沿って書かれてはいるが,ときどき遡行も.
あとがきを見ると,どうやら師匠の若い時分については殆ど資料がないそうなので,伝記の形式とならず,このような回想エッセイの形となるのも,やむをえないかも.
▼
暴露話的内容多し.
満州で行方不明になっていた間のエピソード
慰問団参加の動機は実は空襲が怖かったから
旗本自慢
「道場でなら志ん生に勝てるが,真剣勝負ではかなわない」と評する円生師匠
「芸と商売は別」
「毎晩毎晩高座で『芸』をやっていたら,こっちの体が持ちませんよ」
志ん生師匠の貧乏自慢を,「あの時分,カネのないのはお互いだったんだ.その,お互い金のなかった時分,なけなしの5円貸して,返してもらえなかった身のことは,誰も考えてくれない」とぼやく桂文楽師匠
「志ん生にとっては,戦争と,それに伴う新体制下の風俗も,おのれの自由な創作活動のための,若干の刺激にすぎなかったようだ」
「自分の落語に多少とも新しい色彩を加えることのできる材料にすぎなかった」
志ん生師匠の大津絵に号泣した小泉信三
志ん生師匠を料亭に招くという「一世一代の贅沢」を行った山口瞳
▼
また,他の落語家達のエピソードにも,興味深いものがあり.
現地で臨時妻がいた円生師匠
「雨じゃァねえよ.〔橘屋円喬〕師匠が『鰍沢』をやってるんだよ」
「円左師匠のは,按摩が柳にぶら下がってるときに,その地びたが下に見えるんです.
ところが円喬師のは,「手を離すな,下は何丈とも知れぬ谷間だぞ」「へえッ」と言うと,その断崖の上から,ずウッと柳の木が突き出て,そこへ按摩がぶら下がって,深ァい谷の上へぶらぶらしてるようにあたくしには思えたんです」
国民徴用令逃れのために落語家になった金原亭馬生師匠
昭和落語界を代表する名人、5代目古今亭志ん生の評伝。脳内出血を起こして倒れ、体の自由が利かなくなっていった。晩年を中心に、この天衣無縫な噺家の姿を活写していく。著者の矢野誠一氏は「精選落語会」のプロデュースや落語評論を通じて志ん生や家族と親交を持った。次第に体が衰えていき、寄席に出られる状態ではなくなってくる志ん生。それでも高座への意欲を持ち続けるが、1968年10月9日、矢野氏がプロデュースしていた「精選落語会」への出演を最後に、事実上のの高座引退に追い込まれる。しかし志ん生は高座復帰への夢を捨てきれず、稽古を続けていたという。
1971年、糟糠の妻りん夫人、ライバルにして盟友でもあった8代目桂文楽が相次いで死去、気落ちした志ん生は老衰が目立つようになり、1973年9月21日、83年の生涯を閉じる。いつ亡くなったかも分からないほど安らかな最期であったという。「たったひとりで、いささか乱暴ないい方をすれば、勝手に死んでいったことが、気ままに生きたこの人を象徴しているような気がする」「美しい死に方といっていい」と矢野氏は評している。